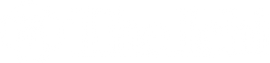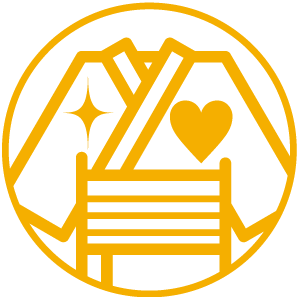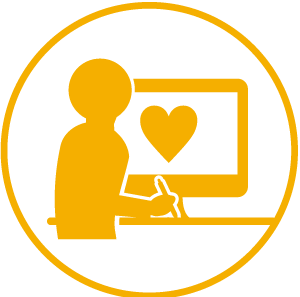夏の季節、花火大会やお祭りなどいろいろなイベントが盛りだくさんですね。涼しげな浴衣を着てお出かけすれば夏気分もさらに盛り上がることでしょう。最近の浴衣はさまざまな模様があります。中でも伝統的な柄「吉祥文様」はいろいろな文様がありますが、その意味はよくわからないという方もいることでしょう。今回は浴衣でよく見かける「吉祥文様」の意味についてご紹介します。ちょっと知っておくと、浴衣を着る時も楽しく着こなせますよ。
吉祥文様とは?
「吉祥(きっしょう)」という言葉を辞書で調べると「良い前兆、めでたいきざし」と書かれています。良い兆し、めでたいしるしという想いを模様で表現したものが吉祥文様です。縁起が良いとされている図柄をベースに、着物の礼装や帯に用いられています。中国やアジア圏の信仰や思想が元となった吉祥文様は、中国独自の模様(代表的な模様として蝙蝠(こうもり))と、日本で生まれた模様(御簾(みす)など)があります。また、アジア圏では縁起のよいとされている図柄でも、ヨーロッパでは不吉な意味を持つものもあります。中国の信仰や風習がルーツの吉祥文様
龍文
龍の姿が描かれている模様です。龍は威厳に満ちた姿が動物の頂点にあるとして、中国では皇帝がきる龍袍に特化されて描かれていました。鳳凰(ほうおう)
龍と同じく伝説上の鳥で、四瑞(麒麟(きりん)・亀・龍・鳳凰)のうちの一つが鳳凰です。平和な世界が訪れた時に現れると伝えられています。平和、安寧着物や浴衣だけでなく風呂敷にも用いられ、雄を鳳、メスを凰と称して「夫婦円満」の意味が込められています。雲気

鶴、亀
「鶴は千年、亀は万年」という言葉にある通り、長生きの象徴として描かれています。また鶴の声は遠くまでよく響き渡るので、天にまで届いているとして「天地を結ぶ存在」でもあります。松竹梅


銀通し変わり織浴衣-紅玉梅
日本で生まれた吉祥文様
御簾
平安時代には寝殿造りの中に御簾がありました。この御簾は貴族の雅やかな文様として用いられています。檜扇
三月三日のひな祭りでお内裏様(おだいりさま)とお雛様(おひなさま)が手にしている扇子で、和歌や絵が描かれている扇子です。当時、流階級しか持てなかったため、豊かさや富の象徴を表しています。御所車(ごしょぐるま)

熨斗(のし)
鮑(あわび)の肉を薄く引き伸ばしたもので、引き出物に添えられて使われますが、この熨斗を何枚も束ねた「束ね熨斗」が吉祥文様としてあります。メンズの浴衣の柄にも見られる他、踊り用の浴衣にも用いられている文様です。薬玉


特選平織り浴衣-彩雲に花輪
宝尽くし
さまざまな宝のアイテムが登場する宝尽くしは、打ち出の小槌や珊瑚や七宝など複数描かれている場合もあれば、一つだけが文様として使われている場合もあります。大きくデザインされたものや小さく全体にちりばめられたものなどがあります。また、日本舞踊の浴衣に多く見られる文様です。南天