平打簪(ひらうちかんざし)
平打簪とは、形が薄く平たい円状の飾りに、1本または2本の足がついたものです。武家の女性がよく身につけた銀製、または他の金属に銀で鍍金したものが主で、これらを指してとくに銀平(ぎんひら)と呼ぶこともあります。円形・亀甲形・菱形・花型などの枠の中に、透かし彫りや毛彫りで定紋・花文などをあらわしたものです。武家の女性は通常自家の家紋を入れますが、江戸後期の芸者の間では、想い人の家紋や名前の頭文字を入れるのが流行したそうです。変わった柄としては団扇・開き扇子・銀杏・桐・笹などを象ったものがあり、素材は木製や鼈甲製、現代ではプラスチック製などがあります。
玉簪(たまかんざし)
玉かんざし とは、耳かきのついたかんざしに玉を1つ挿しただけのシンプルなもので、最もポピュラーな簪(かんざし)。当初実用であった耳かきは、その後デザインとして残されています。飾り玉には珊瑚、瑪瑙、翡翠、鼈甲、象牙、幕末頃にはギヤマン(硝子)、大正時代にはセルロイドなどさまざまな素材が使用されています。京都の花柳界では普段は珊瑚玉を挿し、翡翠玉は夏に用いるしきたりがあります。玉が大きいものほど若向き。簪(かんざし)の足は1本足と2本足のものがあります。
チリカン
芸者衆などが前差として用いる金属製の簪(かんざし)のひとつ。頭の飾り部分がバネ(スプリング)で支えられていて、ゆらゆらと揺れるのが特徴です。飾りが揺れて触れ合い、ちりちりと音を立てることからこの名前がついたそうです。飾りの下側には細長い板状のビラが下がっていて、こちらも小さな音をたてます。
ビラカン
主に金属製で、頭の部分が扇子のような形状をしているものや、丸い形のものがあり、家紋が捺されています。その形状から、「扇」や「姫型」とも呼ばれます。頭の平たい部分の周りに、ぐるりと囲むように細長い板状のビラが下がっているもので、耳かきの無い平打に、ビラをつけたような形状です。現代の舞妓もこれを前挿しにします(芸者になったら使用しません)。その場合は右のこめかみ辺りにビラカン、左にはつまみかんざしを挿します。
松葉簪(まつばかんざし)
主に鼈甲などを使ったシンプルな簪で、全体のフォルムが松の葉のようになっているものを指します。散り松葉に似ているため、付いた名称です。関東(吉原)の太夫用のかんざしセットの中にも含まれます。
吉丁(よしちょう)
耳かきだけで、ほかに装飾のない細長い簪(かんざし)のこと。素材は金属製、鼈甲が主流でしたが、現在では金属やプラスティック製のものが多くなっています。既婚女性は左のこめかみあたりに1本だけ挿すのが定番でした。また、芸者は2本までしか着用が許されていなかったのに対し、遊女は数に制限がなく、多くの吉丁を髮へ装着していたそうです。表面に彫りを施したものや飾りのついたものも数多くあり、当初実用であった耳かきはその後デザインとして残されています。耳かきの形状は、関東では丸型、関西では角型のものを使っていたようです。
びらびら簪(びらびらかんざし)
江戸時代(寛政年間)に登場した未婚女性向けの簪(かんざし)。本体から鎖が何本も下がり、その先にさらに蝶や鳥などの飾り物が下がっている意匠が特徴です。左のこめかみ付近に挿す用途のもので、簪(かんざし)の中でも特に派手かつ華やか。天保年間には、京阪の裕福な家庭の若い子女の間で、鎖を7~9筋垂らした先に硝子の飾り物を下げたゴージャスなタイプが人気を博していたそうです。
つまみ簪(つまみかんざし)
つまみ簪とは、 花かんざし とも呼ばれ、薄地の布を正方形に小さく切り、これを摘んで折りたたみ、竹製のピンセットでつまんで糊をつけ、土台につけて幾重にも重ねたりなどして、花や鳥の文様を形作った簪(かんざし)。多くは花をモチーフにしているので「花簪(はなかんざし)」とも言われます。布は正絹が基本で、かつては職人さんが自ら染めも手掛けていました。現代では舞妓さんが使うほか、子供の七五三の飾りとしてもよく使われています。
鹿の子留(かのこどめ)
手絡(髷を抑えたり飾るための布、鹿の子絞りを施した縮緬が良く使われる)を留めるために使われる短い簪(かんざし)。一般的な簪とは逆に、飾り部分に対して髪に刺す部分が垂直に付いています。年少の舞妓が結う髪型「割れしのぶ」に使われ、銀製かプラチナ製の台に、翡翠や珊瑚などで蝶や糸菊、孔雀、花などの細かい細工が施された高級品です。
位置留
絹製の花弁で作った薬玉のような丸い形の飾りが特徴の簪(かんざし)。
薬玉(くすだま)
絹製の花弁で作った薬玉のような丸い形の飾りが特徴の簪(かんざし)。
立挿し
留め針が長く、鬢の部分に縦に挿す簪(かんざし)。団扇を模した夏用の団扇簪(かんざし)などが有名です。鬢を張り出すようになった江戸中期以降に登場しました。
両天簪(りょうてんかんざし)
簪(かんざし)の両端に対になる飾りがついた形のもの。上方(関西方面)では「両差(りょうざし)」と呼ばれ、江戸では「両天(りょうてん)」と呼ばれていました。銀製の簪(かんざし)で、半ばでふたつの部品に分かれます。一方は錐状で、もう片方はそれが差し込める穴があり、その受け口に差し込んで留めるようになっています。飾りは家紋や花が定番で、裕福な家庭の若い女性や少女が主に使用しました。
銀製葵簪(ぎんせいあおいかんざし)
天保七・八年頃の江戸で流行した簪(かんざし)。銀の平打ちで小さな二葉の葵を模したデザインで、未婚の若い女性から若い遊女までに用いられました。
武蔵野簪(むさしのかんざし)
天保11年から12年に流行した、竹製の本体に鳥の羽を飾りに用いた簪(かんざし)。未婚の若い女性から若い遊女まで使われましたが、主な材質が竹と鳥の羽だけという素っ気無さからか、一般的な人気は得られませんでした。
江戸銀簪(えどぎんかんざし)
江戸中期後半から明治期まで、江戸で広く愛用された銀製で4寸前後の短めの簪(かんざし)。初期のものは5寸から6寸ある長めのものでしたが、江戸後期に入ると短めのものが主流となりました。玉簪(たまかんざし)に珊瑚や砂金石の玉や瓢箪などを飾ったデザインが定番ですが、平打簪(ひらうちかんざし)と同じ技法で、花鳥風月や、俵、団扇など趣向を凝らしたモチーフをつけたもの、逆にまったく飾りのないタイプもあります。素材は銀無垢が一般的ですが、江戸後期には上方風の金メッキを施したものや、下半分は銀で見える部分には赤銅に金象嵌を施したものもありました。
櫛(くし)
髪を梳く櫛の形状です。通常は簪(かんざし)とは区別されますが、 櫛は 「くし」と呼び「苦死」とも解釈されることから、贈り物にする際には目録上を簪、もしくは髪飾りとすることがありました。素材は鼈甲(べっこう)製が多く、木に膠や漆を塗り製作されたものも散見されます。装飾には真珠や螺鈿(らでん)、金箔を使った蒔絵が施されたものなどが多く、また本体部分(峰の部分)は装飾を施すため、幅を広くとってあります。西洋製の櫛(コーム)が本体の両端まで歯があるのに対し、日本の櫛は中央にのみ歯があることが特徴です。これは日本の櫛が、日本髪の額と頭頂部の中間あたりに挿す前櫛として発展したため、前髪の幅に収まる歯数があればよかったためです。
笄(こうがい)
日本髪を結う際の道具のひとつ。通常は簪(かんざし)とは区別されます。もともとは男女ともに髪をまとめるために使われました。男性の場合、日本刀の柄の部分に仕込まれている小さなナイフ状のものがそれに該当し、片側は持ち手で、そこから先端に向って次第に細くなっていく形状です。これに髪を巻きつけて髷を作っていましたが、次第に巻いた後にそのまま髪に残し、飾りとしても使うようになりました。さらに江戸後期では、髷を作る実用性は問われなくなり、出来上がった髷に後から挿し込む髪飾りへと用途が変わっていきました。
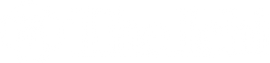





























![[The Ichi(座市)]編集部のオススメ!今週の再入荷商品](http://wargo.jp/cdn/shop/collections/shopify_{width}x.jpg?v=1678940879)

![[The Ichi(座市)]編集部のオススメ!とんぼ玉特集](http://wargo.jp/cdn/shop/collections/Banner-kanzashi_{width}x.jpg?v=1687224735)

![[The Ichi(座市)]編集部のオススメ!水引細工特集](http://wargo.jp/cdn/shop/collections/Banner_Mizuhiki_{width}x.jpg?v=1685944077)